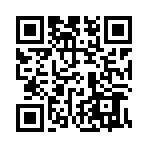2024年10月07日
「筆墨親子」展 宮本信代×上田普

母 宮本信代と二人展を行います。
二人展という形では2011年に京都で行って以来になるのだと思います。
また私の神戸での展示も前回は2019年ですから随分間が空いてしまいました。
大竹民子さんの著書「海の庭」の刊行が去年でしたから
コラボレーションという意味ではそれまでも行っていますが
作品展として一緒に展示するのは久しぶりになりますね。
アート〇美空間Sagaも15周年を迎えたそうです。
その15年の中でも私が一番多く展示をさせて頂いてるのだそうで
この展示でもうひとつ記録更新になりますね。
今回は軸作品を3点用意しています。
また本の仕立ての作品も2点。
本は今の情勢を踏まえた作品を制作しました。
2017年に95歳で亡くなられた京都の三月書房の元店主 宍戸恭一さん(喫茶店仲間でした)
その宍戸さんが研究されていた戯曲家 三好十郎の作品からのモノです。
宍戸さんには「悪人になれ」と言われていました。
戦後左派、右派と思想の観点で活動されていた宍戸さんだからこその言葉です。
要は中道の事で、世間は勝手に右へ、左へと動いています。
自分が真ん中に居てると左右の人からは悪人に見える。
しかし恐れず、群れず、中道を歩めという言葉でした。
私とって大切な言葉。そして今まさにその目が必要な気もしてそれを作品にしてみようと思いました。
私は会期中はずっと会場にいる予定で
宮本信代の在廊日は19日㈯、20日㈰、23日㈬、24日㈭、27日㈰となります。
どうぞ会場まで足をお運び頂けます様よろしくお願い致します。
----------------------------------------------------
筆墨親子 宮本信代×上田普
日時:2024年10月19日㈯~10月27日㈰
11:00-18:00(最終日 16:00まで)
会場:アート〇美空間Saga(神戸 Kobe)
兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-18 観音寺ビル1階
TEL 078-321-3312
書から油絵、水彩、クロッキーと渡り洋画の技法を取り入れた”墨の絵“を描く宮本信代。
その宮本から書を学び、独自の解釈で表現する上田普。
互いに違う方向を歩みつつも筆線、墨の魅力に惹きつけられ独自の表現を模索し続ける親子による二人展。
2024年10月07日
スイスRomainmotierロマンモンティエの個展
色んなモノがブログの方では付いていけていません。
6月の話をしようと思います。
本当ならスイスに居てる間はどんどん更新してと思ってたのですが
全くでした。
軽いし、機能も有りそうだからと思ってたChromebookが
私には使い難かった事も要因のひとつ。普段から慣れておけば良かったのかも知れませんが。
ともかく現地で制作した作品は19点。
それを一堂に集めた展示とパフォーマンスを6月23日に行いました。
私にとってもロマンモンティエの滞在最終日でもあり
オープングを迎えて次の日は帰国の途という日程で
荷物をまとめつつ展示を行う慌ただしい日程になりました。
ともかく展示風景とパフォーマンスを動画にまとめました。
フレームの付いた作品はこのロマンモンティエの姉妹都市である新潟・長岡市の小国和紙を使い制作しています。
ロマンモンティエにある教会はスイスで一番古いと言われる教会で
その側にある発掘された300年、400年前の墓石の拓本(墨は使っていませんが)を取り
そのエンボスを残しつつ書きました。
パネルの作品の展示は難しかったですねえ。
均一に展示できる数量ではありませんし、大きさはランダムですし
なかなかな試行錯誤で展示しました。
これはちょうど開催されていたニコラ・ド・スタールの作品と、美術館からの帰りに見てた
大地、雲、空のレイヤーになっている向こうの風景が合致し、理解できた気がして
その3つのレイヤーを3本の線で表現したモノ。
またそこから3本線で全て表現したのですが
教会のシルエット、山、歴史、人、自然の関わりみたいなモノを表現しました。
また日本で表現してた微妙な墨の表現が石造りの建物には途中から合わない気がして
もっと強いコントラストが表現のできる削り墨を使いました。
向こうの硬水では全然墨が磨れない事も難儀しましたね。
「軌跡」という作品ですが
向こうでメモ、日記の様に書いていた作品です。
記憶がレイヤーになって次の日、明後日のページにも影響されます。
この本は私の持ち込みの紙で大福帳の方法で綴じて頂き、持って行ってました。
京都の経師mucuraさんの仕事です。
最後に置いている石はたぶん元教会の一部だった石。
色、質感が一緒でしたから。
その石の痕跡を留めてこの日記を閉めました。
ズルズルを鼻をすすってると思いますが
どうもこの季節にヨーロッパに行くと私は花粉症になるのです。
この「軌跡」の作品が役立ったのがパフォーマンス。
慌ただしくて全くパフォーマンスの構想が無いまま迎えてしまい。
始まって墨を磨ってる時もまだ考えていました。
ふとこの本を思い出し、頭の中でページをめくりながら行ったのがこのパフォーマンスです。
ざっと70名以上もの方がたぶん居てくれたのだと思います。
私は全く知り合いの居ない所でしたので
レジデンスのイザベルさんがホントに頑張ってくれました。
お出で頂いた方々も長く滞在して頂き、色んな話をしました。
この日から展示が始まり、夏の間展示が行われ
私が居ない時にご覧頂いた方からインスタを通じてメッセージを頂いたりもありました。
それで開催の無事と、私が居なくてもきちんと紹介してくれてる現地のイザベルさんを思い返していました。
他にも現地の小学校でのワークショップや地元の人々へのワークショップを行いましたが
それはまた後日。
最後になりましたが母 宮本信代と二人展を神戸で行います。
その名も「筆墨親子」 宮本信代×上田普
2024年10月19日~10月27日
11:00-18:00(final day ~16:00)
アート〇美空間Saga(神戸 Kobe)
久しぶりの神戸での展示です。
是非足をお運び下さい。



6月の話をしようと思います。
本当ならスイスに居てる間はどんどん更新してと思ってたのですが
全くでした。
軽いし、機能も有りそうだからと思ってたChromebookが
私には使い難かった事も要因のひとつ。普段から慣れておけば良かったのかも知れませんが。
ともかく現地で制作した作品は19点。
それを一堂に集めた展示とパフォーマンスを6月23日に行いました。
私にとってもロマンモンティエの滞在最終日でもあり
オープングを迎えて次の日は帰国の途という日程で
荷物をまとめつつ展示を行う慌ただしい日程になりました。
ともかく展示風景とパフォーマンスを動画にまとめました。
フレームの付いた作品はこのロマンモンティエの姉妹都市である新潟・長岡市の小国和紙を使い制作しています。
ロマンモンティエにある教会はスイスで一番古いと言われる教会で
その側にある発掘された300年、400年前の墓石の拓本(墨は使っていませんが)を取り
そのエンボスを残しつつ書きました。
パネルの作品の展示は難しかったですねえ。
均一に展示できる数量ではありませんし、大きさはランダムですし
なかなかな試行錯誤で展示しました。
これはちょうど開催されていたニコラ・ド・スタールの作品と、美術館からの帰りに見てた
大地、雲、空のレイヤーになっている向こうの風景が合致し、理解できた気がして
その3つのレイヤーを3本の線で表現したモノ。
またそこから3本線で全て表現したのですが
教会のシルエット、山、歴史、人、自然の関わりみたいなモノを表現しました。
また日本で表現してた微妙な墨の表現が石造りの建物には途中から合わない気がして
もっと強いコントラストが表現のできる削り墨を使いました。
向こうの硬水では全然墨が磨れない事も難儀しましたね。
「軌跡」という作品ですが
向こうでメモ、日記の様に書いていた作品です。
記憶がレイヤーになって次の日、明後日のページにも影響されます。
この本は私の持ち込みの紙で大福帳の方法で綴じて頂き、持って行ってました。
京都の経師mucuraさんの仕事です。
最後に置いている石はたぶん元教会の一部だった石。
色、質感が一緒でしたから。
その石の痕跡を留めてこの日記を閉めました。
ズルズルを鼻をすすってると思いますが
どうもこの季節にヨーロッパに行くと私は花粉症になるのです。
この「軌跡」の作品が役立ったのがパフォーマンス。
慌ただしくて全くパフォーマンスの構想が無いまま迎えてしまい。
始まって墨を磨ってる時もまだ考えていました。
ふとこの本を思い出し、頭の中でページをめくりながら行ったのがこのパフォーマンスです。
ざっと70名以上もの方がたぶん居てくれたのだと思います。
私は全く知り合いの居ない所でしたので
レジデンスのイザベルさんがホントに頑張ってくれました。
お出で頂いた方々も長く滞在して頂き、色んな話をしました。
この日から展示が始まり、夏の間展示が行われ
私が居ない時にご覧頂いた方からインスタを通じてメッセージを頂いたりもありました。
それで開催の無事と、私が居なくてもきちんと紹介してくれてる現地のイザベルさんを思い返していました。
他にも現地の小学校でのワークショップや地元の人々へのワークショップを行いましたが
それはまた後日。
最後になりましたが母 宮本信代と二人展を神戸で行います。
その名も「筆墨親子」 宮本信代×上田普
2024年10月19日~10月27日
11:00-18:00(final day ~16:00)
アート〇美空間Saga(神戸 Kobe)
久しぶりの神戸での展示です。
是非足をお運び下さい。