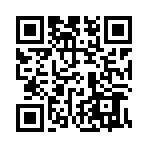2011年10月29日
木津川アート2011

昨年に引き続きの参加と成りますが
アートイベント「木津川アート2011」に
今年も参加させて頂く事に成りましたのでお知らせさせて頂きます。
木津川市は奈良時代からの長い歴史を持ち
京都と奈良の県境の町です。
その町に点在する、アートを感じさせる場所を
作家自ら探し、そこに作品を展示する町ぐるみのアートイベントです。
昨年は、取り壊し予定の銀行、江戸時代からの旧家、里山、幻の大仏鉄道跡地等が
展示場所と成り、地元のみならず関西近郊の方々、なかには関東からも
足を運んで頂く事が出来、美術評論家からも高評価を得る事が出来ました。
今年は隣接するJRの3駅(木津駅、上狛駅、加茂駅)から歩ける範囲内に
展示場所を点在させる催しと成り、作家も今回は多数の応募があったらしく
厳しい審査から選ばれたツワモノ達が揃っている模様。
私の展示する上狛駅付近は
江戸時代からの環濠集落の様子を残す旧家群。
福寿園を中心としたお茶屋問屋ストリート。
戦火を免れる為に漆喰壁を墨書きした倉庫等、
散策するには持ってこいのスポットに成って居ります。
どうぞ古い街並み散策とアートを感じる一日を楽しんで頂く絶好の機会として
足をお運び頂ければと思います。
*イベント会場周辺にお出で頂きますとパンフレット、チラシ等が
配られて居りますので、そちらを手に歩いて頂けますと迷わず楽しんで頂けると思います。
木津川アート2011 http://kizugawa-art.com/
日時11月3日(祝)~13日(日)
10時~17時(最終日16時迄)
<上田普作品展示場所 山城JA倉庫>
2011年10月19日
年賀状デザイン販売中!
はやくもこんな時期がやって来ました。
「もう年賀状!」そんな声が聞こえてきそうです。
さて今年も年賀状用の文字デザインをやらせて頂きました。
来年は辰年ですので「辰」「龍」「りゅう」の文字を4パターンで掲載されております。
こんなんあっても面白いよね。 と思って
画像の「どらごん」も提案してはみたのですが
ボツに相成りました(ハハ)。
どんな物が採用されたのかは見てのお楽しみという事で。
多くの書店で既に販売されて居りますので
お立ち寄りの際は是非ご覧頂き、宜しければ来年の賀状にお使い頂けると嬉しです。


年賀状素材集 和の彩り 辰年版
アスキー書籍編集部 編
定価:1,239円 (本体1,180円)
形態:A4変 (192ページ)
付属品:CD-ROM×1枚
2011年10月16日
奇書「龍潭譚」完成!
題字を書かせて頂いた絵草子「龍潭譚」が200部限定で完成致しました。
以前紹介させて頂きました
現在金沢の泉鏡花記念館で開催している
「泉鏡花×中川学 龍潭譚 Mac×Illustratorでよみがえる幻妖の美の世界」展は
こちらの絵草子(絵本)が元案に成っています。
画像では分かりにくいかも知れませんが
表裏表紙は金属の錫(スズ)で、題字は銀箔押されています。
泉鏡花の幽玄な世界観を中川学さんの和ポップなイラストで見事に表現され
その各章の空気感をハンマーダルシマーとシンセサイザーで誘って下さる山口智さんの音楽。
装丁、デザイン、アイデアでド肝をヌイてくれたのはiD.の泉屋宏樹さん。
こだわりの本を実現して下さり、より高みまで表現して下さった今泉版画工房さん。
紙の良さ、印刷の美しさも抜群です。
関わる事が出来た事が非常に嬉しく感じる
印刷からクリエイターまで全て関西で作られた作品とも呼べる本が完成しました。
この題字を書くにあたって
読めないほど崩してもイイよと言われはしましたが
こういう題字は読めないと意味が無いと思いましたし
相手は文豪 泉鏡花です。下手な書は書けません。
幽玄さと、品格みたいな物を思いえがいていました。
難しいのは文字的に「潭」と「譚」が続く事。
同じ様に書いてしまっては変化が無くおもしろくない。
ヘンとツクリを上下に動かしたり、離してみたり、奇をテラってみたり。
色々と試行錯誤し書き上がりました。
この絵草子「龍潭譚」にはオフィシャルHPもあり
詳細な紹介がありますので是非ご覧頂き、お手にして頂ければと思います。
ちなみに現在書店に並んでいるデザイン系雑誌「アイデア」にも紹介されています。
お立ち寄りの際はそちらも是非ご覧下さい。

絵草子「龍潭譚」 オフィシャルHP: http://www.ryutandan.net/
2011年10月11日
夏目漱石の句
「秋の江に 打ちこむ杭の 響かな」
夏目漱石
(澄みわたる秋空。広い入江。そこに打ちこまれる杭の音が遠くから響いてくる。)
教室で用いた題材です。
半紙横半分にして書いてもらいました。
書道教室って漢字を書いたり、創作をしたりという内容が多いですが
実用というジャンルもあって
実際に生活の中で筆を使う事を考えると
こういった小筆の場面の方が多いですよね。
そういう事を考えて
崩し過ぎないで、漢字も平仮名もある題材を取り上げます。
手紙、年賀状、芳名を求められる時
そういう時の為の練習ですね。
小筆は慣れが大事という所があるので
持つ機会が多ければ多いほど上手く成ると思います。

書道教室 http://hiroshiueta.kyo2.jp/e84455.html
2011年10月07日
才能の有無

縁あって京都造形大内のギャルリ・オーブで開催されている
「庭の見世物小屋 東義孝」展を見てきました。
東義孝さんは1977年生れで、京都造形大で学ばれた後
東京のギャラリーと契約し、日本での個展の他ニューヨークでも活躍され
美術館での企画展等にも展示されていましたが
2010年惜しくも亡くなられた作家です。
そんな彼の回顧展としての展示が母校で開催されているという事でした。
私もアートイベントを介して知り合った作家さんで
若くして亡くなってしまわれた方がいらっしゃいます。
活躍出来ていた訳でもなく
ホントにこれから頑張って行きましょうという方が
絵だけを残して亡くなられたという現実に
いったい何が出来たんだという虚しさと
残念さが入り交じり胸が痛く成りました。
東さんの作品も活躍されていたとは云え
まだまだ模索されてた跡は見えましたし
徐々に腕が上がっている所も、洗練されてきている所も目に見えました。
しかし、正に志半ばで筆を置く事に成ってしまった事に対する
残念さが感じられました。
その人に才能があるのか無いのかと
よく言われますが
そんな事は誰にも分かりません。
芸術の世界にも正解がありませんから
その作品が社会に強い影響を与えた人、マーケットにウケた人は
後に才能があったと言われるでしょう。
言える事は
その可能性を持っていた人が
残念ながら亡くなられたという事。
私も同じ道を志す者として色々考えさせられる機会を頂きました。
今彼が願う事ととすれば
彼が残した作品がより多くの方の目に触れてくれる事でしょう。
残り少ない日程ですが、是非お近くの際はお立寄り頂ければと思います。

庭の見世物小屋 東義孝
日時 10月10日(月・祝)まで
11時~18時(最終日16時迄)
入場料 なし
休館日 なし
ギャラリートーク
10月9日(日) 15:00~16:30
会場: ギャルリ・オーブ(京都造形大学 内)
担当: 榎本耕一(アーティスト)、東明子(パートナー)
参加料 無料 ・申込不要